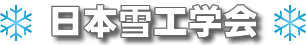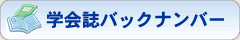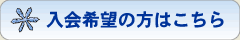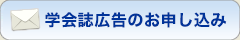会長挨拶
会長就任にあたってのご挨拶
上村 靖司
Seiji KAMIMURA
はじめに
このたび日本雪工学会の第19期会長を拝命いたしました。諸先輩方が築きあげ継続してきた学会を受け継いで一層の発展を目指してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
歴代会長を振り返ると、初代の内山和夫先生から、首藤伸夫先生、吉野博先生、植松康先生と東北大学の先生方が続き、第5代福原輝幸先生(当時福井大学教授)、第6代沼野夏生先生(東北工大名誉教授)、第7代高橋徹先生(千葉大学教授)とバトンが渡されてきました。1986年の学会発足以降会員は順調に増えていき、1990年代には500名を優に超える会員数を数えたものの、その後2014年頃にかけて減少傾向が続き250名ほどにまで縮小してきました。
この学会にとって困難な時期に就任された福原元会長、沼野元会長、高橋前会長のもと、役員を中心に会員の協力を仰ぎながら体制の再構築をはかり、2022年2月時点で会員数257名と下げ止まりが顕著となりました。そして財務的にも少なくない余剰がでるほどの健全な運営ができるまでになりました。むしろ安定した会員動向と財務的な余剰を活かし、積極的に打ってでるべきタイミングにあるように感じています。
いまから18年前の2004年10月に発生した新潟県中越地震は、豪雪地帯で冬の直前に震災を経験するという未曽有の事態となりました。深刻なダメージを受けた住居や建物だけでなく、消雪パイプなどの冬季道路交通を支えるインフラが破壊され、波打った道路では除雪車による作業が困難になることも予想されました。
中越地震・平成18年豪雪の経験
このとき、震災から2か月後に突入する本格的な冬を前に強い二次災害の懸念を抱いた著者らは、全国の研究仲間に呼びかけ、冬に起こり得る二次災害の想定、そして間に合う応急対策の検討に取り組んでいました。多くの仲間の協力を得て、かつてないスピード感で調査、分析、啓発文書作成、発信と進めましたが、如何せん、経験の浅いメンバーだけでは想像しきれないこと、そして具体的に何をして良いかわからないことだらけでした。ふと思い立ち、すでに一線から退かれていた栗山弘(元雪害実験研究所・所長)先生に電話で相談をしました。開口一番、「学者は肝心なときに全く役に立たない」とぴしゃりと言い放たれたことを鮮明に思い出します。「学者は理屈ばかりで、現場で使える具体的で現実的な解はもってない」と。確かにその通り。率直に思いました。2011年に学会誌に寄稿した「私の視点」で述べていますが、現在の冬の雪国の暮らしを支えている基幹技術に、工学研究者の貢献は実に小さいと思っています。道路除雪・融雪にしても屋根雪処理にしても、現場技術者と民間発明家の挑戦と工夫から生み出された「現場技術」が未だ基軸となっています。理屈抜きに目の前の問題を如何に乗り越えるかに真摯に向き合ってきた人々の努力の上に私たちの今が立脚しているのです。
震災直後の冬は皮肉にも18年ぶりの豪雪となりました。そしてその翌年の平成17年12月からは、まさに記録的な豪雪となりました。「平成18年豪雪」です。全国で152名もの命が失われ、その大半が除雪作業中の高齢者でした。半世紀以上前から始まっていた豪雪地帯の過疎化・高齢化・人口減少という慢性病が、久しぶりの豪雪で一気に顕在化したのです。後の検証で除雪の担い手不足が指摘され、精力的に担い手期確保の方策が国レベルで議論されるようになりました。筆者らも除雪ボランティアの本格的な受入れ体制を作るために「越後雪かき道場」を翌冬から始め、全国に仲間の輪を広げてきました。しかし、雪害犠牲者は毎年増え続けています。被害に遭遇しうる潜在的な人口で除した人口比では風水害をも上回り、横綱級の地震・津波を除けば、わが国で最も深刻な災害と言っても過言ではないでしょう。
真に雪国の課題解決と発展に貢献する
「工学の工の字は、天を表す上の線、地を表す下の線、そして天と地を繋ぐ縦の線でできている」とは、計測工学の大家 土屋喜一先生の言葉です。天すなわち自然と、地すなわち人間社会をつなぐのが工学なのだと。「工学」を冠する本学会が取るべき姿勢を見事に示しているのではないでしょうか。
初代会長の内山先生は、学会誌初号で「研究者・技術者はもちろん(中略)国又は地方自治体並びに市民の参加と協力によって(中略)雪害対策の樹立や豊かな雪国の地域づくりに貢献する成果を期待する」と書かれています。つまり、研究者・技術者を中核とする学会ではあるが、国・自治体、市民を巻き込み、真に雪国社会に貢献する学会を目指そう、ということです。
豪雪地帯の過疎化・高齢化、人口減少は全国を10~20年先行し、雪に関わる人的被害は大雪年には100人を超え、気象の激甚化に伴う大規模車両滞留の頻発など新たな問題も深刻化しています。雪国限らず、H26の関東地方の大雪被害に対する保険金支払額は歴代8位で、H28熊本地震に匹敵しH30西日本豪雨の1.5倍にも達します。つまり雪の問題は決して雪国だけのものではなく、そしてまだ解決していないのです。
このような現状認識から、以下の3本の柱に沿って、今後の活動を展開して行きたいと考えています。
(1) コミュニティ再構築:
- 行政、公的機関等との連携・共同体制の再構築
- 民間会員・業界団体等との連携・共同体制の強化
(社会課題を共有し解決する仲間を増やす)
(2) オープン化の推進
- 学会員のみにこだわらない活動・運営の展開
- アウトリーチ、他団体と連携・共同・協働の推進
(3) 知の循環の促進
- 市民、社会、公的機関との社会課題の共有
- 研究者グループの形成促進と研究活動の活性化
- 出版事業の活用促進など、知の社会還元の展開
これらの積極的な活動を推進する上での原資となる学会財務上の内部留保は、幸い潤沢にあります。会員諸氏からも積極的な提案と具体的な活動推進を期待いたします。真に雪国の課題解決と発展に貢献できる学会を目指し、皆様とともに取り組んでいきたいと思います。